不用品回収業者が知っておくべき関連法令の罰則まとめ
不用品回収業者は廃棄物処理法をはじめとする法律に則って営業しなければなりません。ではこれらの法律に違反した場合、どのような罰則を受けることになるのでしょうか。ここでは不用品回収業者に関係する4つの法律の主な罰則をまとめて紹介するとともに、罰則を回避するための考え方を、各管轄行政への問い合わせをもとに解説します。
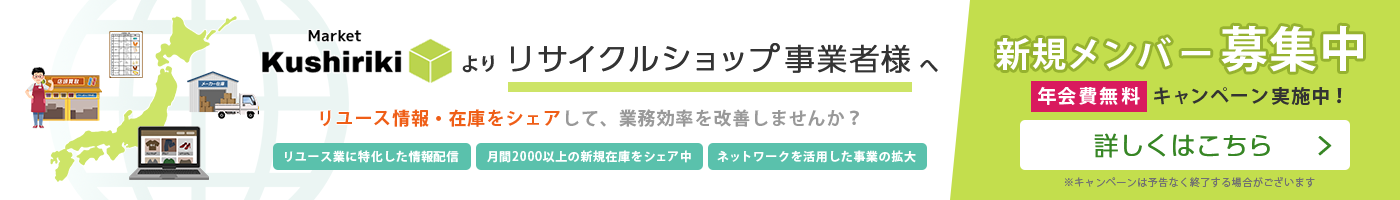
不用品回収業者は廃棄物処理法をはじめとする法律に則って営業しなければなりません。ではこれらの法律に違反した場合、どのような罰則を受けることになるのでしょうか。ここでは不用品回収業者に関係する4つの法律の主な罰則をまとめて紹介するとともに、罰則を回避するための考え方を、各管轄行政への問い合わせをもとに解説します。
不用品回収業者などが出張買取・出張回収先で出くわす問題の一つに、駐車場所の問題があります。何も考えずに車を離れてしまうと、少しの間でも駐禁切符を切られる可能性がありますが、だからと言って車に待機させるために人を一人増やすわけにもいきません。ここではこの問題に対処するための正しい路上駐車の考え方について解説します。
古物商許可を取っていても、事業を他の会社へ譲渡する場合や会社分割、新しい営業所を開設するなどを行う場合、新たに古物商許可申請が必要なことがあります。ここでは、このような特殊な事例ごとに、古物商許可申請や手続きについて解説します。
リサイクル業を営む上で欠かせない古物商の許可の申請は、難しいものではありませんが、細かな規定も存在するため、提出書類や申請場所を詳しく解説します。
「ペットボトルの再生フレークを加工する事業を始めるためには、特別な許可が必要ですか?」先日こんな質問がJRITSに実際に寄せられました。ここではこの質問に答えるべく、公的機関への問い合わせを実施。その回答内容をもとに、古物営業法や廃棄物処理法の観点から許可の必要性について徹底的に解説します。
リサイクル業を営むには古物商許可が必要であり、古物商許可を持たずに営業をすると罰金を科せられてしまいます。さまざまな状況別に、古物商の許可が必要か不要かをしっかりと確認しておきましょう。
2018年4月25日に交付された改正古物営業法が、2018年10月24日から順次施行されていきます。今回の改正には不用品回収業者に深く関わるものがあるだけでなく、対応を間違えると許可の取り消しにつながるものもあります。そのためしっかりと改正内容を理解したうえで、確実に対応する必要があります。ここでは実例も交え4つの変更点について解説します。
古物商許可においての古物は、単に「古い物」だけではありません。未使用であっても、一度人の手にわたった新古品も古物である反面、航空機など大きな機械は中古品でも古物ではないのです。古物商許可における「古物」について詳しく解説します。
リサイクル業者が注意すべき法令として、古物営業に必要な【古物商許可(古物営業法)】、産業廃棄物の取扱業に必要な【産業廃棄物許可(産業物処理法)】、小型家電の回収業に必要な【小型家電リサイクルの事業者認定(小型家電リサイクル法)】について徹底解説しています。
古物商と同じで古物市場も公安委員会の許可申請が必要です。自分でも警察署経由で申請可能ですが、法律事務所などに依頼して申請する方法もあります。産廃の収集運搬許可や金属くず商許可なども、必要に応じて申請しておきましょう。